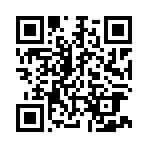2012年07月09日
昔、お茶は薬として飲まれていたのです
笑顔配達人☆和茶倶楽部なごみです。
今日は、ちょっとお堅いお話です。
先日、NHKの「平清盛」を見ていたら、宋(中国)の時代の皇帝など(高位の方々)の喫茶を表現している場面がありました。
太宰府に清盛が出向いた際、太宰府の長官が清盛をもてなしたシーン。
はっきり言って、釘づけでした・・・私。
終了後も暫く興奮して・・・誰かに伝えたくて・・・伝えたくて。
思わず、私がやっている、「お茶講座」でも話してしまいました!!
九州は、大陸に近い為、当時中国&朝鮮などからの喫茶の風習が、渡ってきて、京の朝廷への喫茶の伝播とは、別経路で伝わってきている可能性が高く、また、独自の文化を形成していた可能性もあります。
けれども、歴史的書物は常に、政治の中心地や、太宰府などの要所の文献などがメインのため、庶民の生活までは分かりにくく、平安時代の喫茶に関してはなかなか記述がないのが現状でその詳細はあまり分かっていません。
基本、今は、茶の伝来は、空海や最澄などの遣唐使として唐に渡たった高僧が持ち帰ったものが初めとされています。
当初は、唐の時代の喫茶法がそのまま伝播し、葉をそのまま蒸して、固め、保存が効く状態にしたものを、薬研で引いて、粉末にし、それを服して飲んでいたというのが主流でした。
やがて、高位の方々の中では、茶筅の原型のようなものが登場して、(だんだん茶道に発展していく・・・。)抹茶をたてて飲むようになります。
そんな茶の歴史の一遍を「平清盛」・・・平安後期で見れたのは、とても嬉しくて、その夜は結構興奮してしまいました。
そして、この後、臨済宗の開祖である「栄西」が登場し、『喫茶養生記』を源実朝に献上します。
本格的に、茶に関する書物が、日本で初めて書かれるのです。


『喫茶養生記』は、
茶は養生の仙薬なり。延齢の妙術なり。・・・・・で始まります。
お茶は、昔から、薬として飲まれていたのです。
追伸
平清盛・・・人気がないようですけど、我が家では、第1話から欠かさず見ていますが、正直、とても面白いと思って見ています。
貴族の時代をやることも珍しいので、余計に力が入って見ています!
これから、どんな展開になるのか楽しみです♪
今日は、ちょっとお堅いお話です。
先日、NHKの「平清盛」を見ていたら、宋(中国)の時代の皇帝など(高位の方々)の喫茶を表現している場面がありました。
太宰府に清盛が出向いた際、太宰府の長官が清盛をもてなしたシーン。
はっきり言って、釘づけでした・・・私。
終了後も暫く興奮して・・・誰かに伝えたくて・・・伝えたくて。
思わず、私がやっている、「お茶講座」でも話してしまいました!!
九州は、大陸に近い為、当時中国&朝鮮などからの喫茶の風習が、渡ってきて、京の朝廷への喫茶の伝播とは、別経路で伝わってきている可能性が高く、また、独自の文化を形成していた可能性もあります。
けれども、歴史的書物は常に、政治の中心地や、太宰府などの要所の文献などがメインのため、庶民の生活までは分かりにくく、平安時代の喫茶に関してはなかなか記述がないのが現状でその詳細はあまり分かっていません。
基本、今は、茶の伝来は、空海や最澄などの遣唐使として唐に渡たった高僧が持ち帰ったものが初めとされています。
当初は、唐の時代の喫茶法がそのまま伝播し、葉をそのまま蒸して、固め、保存が効く状態にしたものを、薬研で引いて、粉末にし、それを服して飲んでいたというのが主流でした。
やがて、高位の方々の中では、茶筅の原型のようなものが登場して、(だんだん茶道に発展していく・・・。)抹茶をたてて飲むようになります。
そんな茶の歴史の一遍を「平清盛」・・・平安後期で見れたのは、とても嬉しくて、その夜は結構興奮してしまいました。
そして、この後、臨済宗の開祖である「栄西」が登場し、『喫茶養生記』を源実朝に献上します。
本格的に、茶に関する書物が、日本で初めて書かれるのです。


『喫茶養生記』は、
茶は養生の仙薬なり。延齢の妙術なり。・・・・・で始まります。
お茶は、昔から、薬として飲まれていたのです。
追伸
平清盛・・・人気がないようですけど、我が家では、第1話から欠かさず見ていますが、正直、とても面白いと思って見ています。
貴族の時代をやることも珍しいので、余計に力が入って見ています!
これから、どんな展開になるのか楽しみです♪